発達の違いってどう対応すればいいの?
そもそも発達の凸凹って何?

このお悩み
児童発達支援で保育士をしている私が解説します!
発達の凸凹、一人一人に合わせて保育することは難しいですよね。
この子はできるけど、この子はまだできない・・なんてことは当たり前にあるのです。
この記事を見れば、定型発達の子どもたちに見られる「凸凹(でこぼこ)」の違いについてわかるようになりますので、ぜひ最後まで見てくださいね。

定型発達にも違いがある!その問題とは?
「定型発達の子どもなら、みんな同じように成長するのでは?」と思っていませんか?
実は、発達には個人差があり、全員が同じ道をたどるわけではありません。
たとえば、
- 言葉を早く話す子もいれば、運動能力が先に発達する子もいる
- 指先を使う動作が得意な子と苦手な子がいる
- 周囲との関わりが得意な子とそうでない子がいる
こうした違いを理解せずに「この年齢ならできて当然」と決めつけてしまうと、子どもにとってストレスになってしまいます。

定型発達の違いを理解することで得られるメリット

定型発達の子どもにも個人差があることを知ると、保育や育児の対応が柔軟になります。具体的には、以下のメリットがあります。
- 子どものペースに合わせた保育ができる
- 「できる・できない」ではなく、成長の過程を大切にできる
- 発達の個人差を理解し、保護者との連携がスムーズになる
定型発達の流れと順番の違いを理解しよう
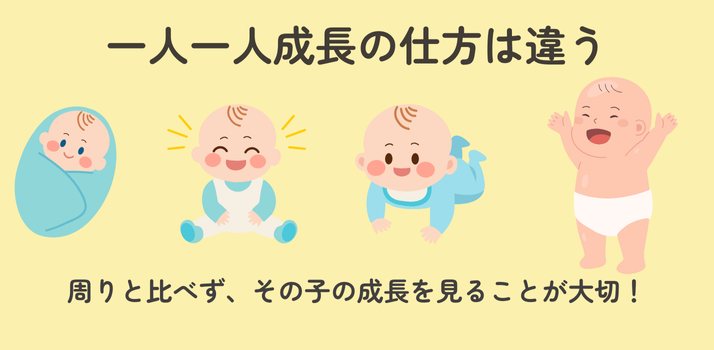
発達の流れは一方向ではない
子どもは一般的に、「大きな動作」から「細かい動作」へ発達していきます。
➡ (例) 首がすわる → 寝返り → はいはい → つかまり立ち → 歩く
しかし、この順番が必ずしもすべての子どもに当てはまるわけではありません。
違う順番で発達することもある
例えば、
- 歩くのが早いけれど、言葉はゆっくりな子
- 指先を使った遊びが得意だけど、大きな動作が苦手な子
このように、発達の順番が異なることは珍しくありません。
保育士ができること

では、こうした違いを保育にどう活かせばよいのでしょうか?
子ども一人ひとりのペースを尊重する
大人になっても人によってできることやできないことがあります。
子どもも同じで「○歳だからできるはず」ではなく、その子のペースがあります!
例えば、言葉が遅い子には、
☑︎ 無理に話させようとせず、気持ちを代弁する
「○○と思ったのかな?」「楽しかったね」など
☑︎ ジェスチャーを使いコミュニケーションをとる
同じ立場になって体を使って表現してみる
といった対応をすると、安心して成長できます。
保護者との情報共有を大切にする
保護者も発達の違いに不安を抱えていることが多いです。
ささいな成長を伝えたり、ポジティブな伝え方をすることで安心してもらえます。
☑︎「最近、○○ができるようになりましたね!」とポジティブな報告をする
保護者では気づきにくい小さな変化も伝えるとGOOD!
👶「はよ!(おはよう)って言ってくれたんです!」など
☑︎「スプーンの持ち方、今バキュン持ちを練習しています!」など
いろんな方法を提案する。
こうした対応で、保護者との信頼関係も築けます。
最後に
定型発達の子どもたちにも一人一人のペースがあり、発達の順番が違うこともあるということを理解することで、より柔軟な保育が可能になります!
「○歳だからこうでなければいけない」という固定観念を持たずに、子ども一人ひとりのペースを大切にすることが大切です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
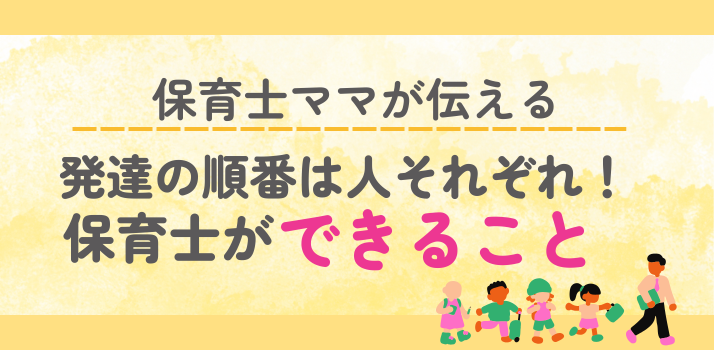
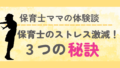

コメント